
RECRUITING SITE
子ども達と関わっていると感性が磨かれ、自身も共に成長できる仕事だと思います
TAKUMI(たくみ)武蔵浦和教室
Mさん(教室マネージャー)
2022年入社
現役マネージャーへインタビュー
TAKUMI(たくみ)武蔵浦和教室
Mさん(教室マネージャー)
2022年入社
現役マネージャーへインタビュー
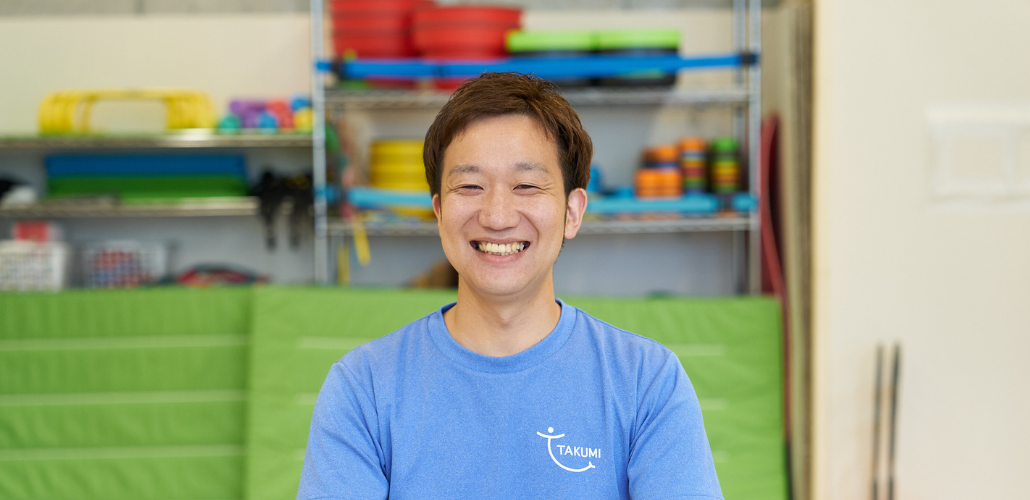
01
MさんがTAKUMI(たくみ)に興味きっかけを教えてください。
前職ではスポーツメーカーの販売員をしていましたが、もともとは幼児体育に携わっていました。一度現場を離れたものの、子どもが好きな気持ちは変わらず、「本当に自分がしたいことは何か」と考えていたときに、運動療育を行っているTAKUMI(たくみ)を知りました。
体育指導をしていた頃は、障がいについて深く考えたことがありませんでした。振り返ると、関わってきた子どもたち一人ひとりの「個」をしっかり見ていたかというと、どちらかというと勢いで指導を進めていた部分もあったように思います。
今一度、運動という側面から子どもたち一人ひとりを大切にしながら向き合っていきたい。そう考え、TAKUMI(たくみ)への入社を決めました。
02
TAKUMI(たくみ)での仕事内容を教えてください。また、仕事をする上で大切にしていることを教えてください。
主となる仕事内容は、発育や発達に悩みごとがある子ども達へ「運動」をツールに療育を行います。またご家族へのサポートや子ども達が通っている園や学校等への地域連携にも努めています。仕事をする上で大切にしていることは「遊び心」です。子どもは遊びの天才なので、自分も子ども達の世界観を学び、遊び心を持って関わっています。支援においても「この運動、もっとこうしたら楽しいのではないか」と常に考え、教室の皆で話し合っています。
03
現在のポジションで最も重要だと思う能力やスキルは何ですか?それを向上させるためにどのような取り組みをしていますか?
現在、教室のマネージャーを務めていますが、何事にも興味・関心を持ち、「知る」ことが重要だと考えています。社会人になったばかりの頃、当時の上司から「無知は罪だ」という言葉をいただきました。その言葉は今でも心に残っています。
子どもたちに好きな食べ物や遊びを聞くように、一緒に働く職員に対しても、何気ない会話を通じてその人の考えや価値観を知ることを意識しています。また、やり取りの中で知らなかったことはそのままにせず、自ら調べることで知識を深め、さらにそれを人と共有・共感することで信頼関係が築けるのではないかと考えています。
福祉事業やマネジメントについて、まだ学ぶべきことは多くありますが、周囲の方々に積極的に聞きながら、自身の知見を広げていけるよう努めています。
04
Mさんの職業人生で最も大きな成長を遂げた瞬間は何ですか?その経験から学んだことは何ですか?
幼児体育の指導者だった頃、幼稚園の新規契約に携わる機会がありました。契約を決めるための一環として公開指導を担当させていただき、当時は緊張のあまり食事も喉を通らなかったことを覚えています。それでも何とかやり遂げ、無事に契約につなげることができました。
この経験を通じて学んだのは、「事前準備」の大切さです。公開指導に向けて指導案を作成し、模擬指導を繰り返し、自分の指導をビデオに撮って何度も見返しました。緊張はありましたが、入念な準備があったからこそ良い結果につながったのだと思います。
また、この成功は自分一人の力ではなく、上司をはじめ、同期や周りの方々の支えがあってこそ実現できたものであり、今でも深く感謝しています。
05
過去の職場でチームメンバーと対立した経験はありますか?もしあれば、その解決策や結果について教えてください。
言い争いには至りませんが、療育においてお互いの意見が衝突した経験はあります。しかし、それは双方が子どもたちのことを第一に考えていた結果なので、良い意味で捉えています。療育に完璧はないと考えているからこそ、各々の価値観を今も大切にしています。お互いの言葉に耳を傾け、思いを共感し合いながら、皆で意見を出し合う教室が理想だと考えています。
06
新しい知識を習得する方法やどのように学んでいるかを教えてください。
入社したての頃は、療育に関する知識はもちろん、利用者様がどのようにTAKUMI(たくみ)と契約し、サービスを利用しているのかも全く分かりませんでした。そのため、日々先輩職員に質問したり、教室の書類に目を通すことに多くの時間を費やしていました。その中で知識を習得する上で大切にしていることは、児童発達支援管理責任者が作成してくださっている個別支援計画に目を通すことです。計画には一人ひとりに合った具体的な支援方法が記されており、時には自身の支援が迷走してしまった時に原点に立ち返らせてくれます。また、支援の幅を広げるために、インターネットやSNSも参考にしています。
07
Mさんの理想や価値観は何ですか?当社のバリューや文化との一致や違いについてどう考えていますか?
療育はスポーツや勉強などと違い、成果や結果が目に見えづらく、また時間がかかるものだと感じています。しかし、私たちとの関わりが子どもたちの自信や今後の人生の一助となることができたら嬉しく思いますし、それが理想だと思っています。抽象的な部分もありますが、その一助になるために、どれだけ多角的にアプローチできるかを考え、当社のバリューにもあるように『自身も楽しみながら』子どもたちと向き合っていきたいと考えています。
08
今後TAKUMI(たくみ)・イニシアス株式会社はどのようになっていってほしいですか?
支援を行うにあたり、職員の知識や対応力が深まり、運動療育の事業所としての魅力が地域に広がることを嬉しく思います。そのために、私自身も常に支援内容を研鑽し、皆で手を取り合いながら現場の充実に努めていきたいと考えています。
09
当社での長期的なキャリアのビジョンや目標は何ですか?その達成に向けてどのような準備や計画をしていますか?
子どもたちが個性を活かし、伸び伸びと生活できるように、『TAKUMI(たくみ)』をより地域に広めていきたいと考えています。実際に行った活動としては、近隣の子育て支援センターで親子プログラムを実施してまいりました。また、引き続き療育や福祉事業の知見を深め、児童発達支援管理責任者になることも目標の一つです。
10
児童福祉業界を目指す方へメッセージをお願いいたします!
子どもたちの世界観は、学びと発見に満ちていると常々感じています。もちろん、この仕事は体力を使い、大変なこともありますが、子どもたちと関わることで感性が磨かれ、自分自身も共に成長できる仕事だと思います。また、遊び心を大切にし、人のために尽くすことができる方々とご一緒にお仕事ができることを楽しみにしています!

